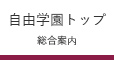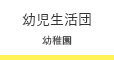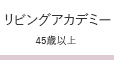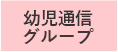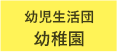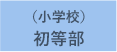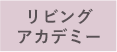夏の終わり頃、以前空き地だったところに家が建ち、書斎の窓とその家の裏口が向かい合わせになりました。どんな家族なのかまだはっきりしないのですが、生まれて間もない赤ちゃんと3歳くらいの女の子がいるようです。
元気な赤ちゃんと女の子です。窓を開け放っていると時々赤ちゃんとそのお姉ちゃんの泣き声がします。
机に向かっているとその声が気になって仕方がありません。密閉型の高価なイヤホーンを奮発して、耳をふさぐのですが気になってしようがありません。自分の神経が少しおかしくなっているのではないかと思うくらいでした。
そんな時に、織田作之助の短編「蛍」のこんな一節に出会いました。
夏の夜、主人公の寺田屋お登勢の家の庭から赤児の声が聞こえてくる場面です。
「登勢は遠くで聴える赤児の泣声が耳について、いつまでも目が冴えた。生まれて十日目に死んだ妹のことを想い出したためだろうか。ひとつには登勢はなぜか赤児の泣声が好きだった。父親も赤児の泣声ほどまじりけのない真剣なものはない。あの火のついたような声を聴いていると、しぜんに心が澄んで来ると云い云いしていたが、そんなむずかしいことは知らず、登勢は泣声が耳にはいると、ただわけもなく惹きつけられて、ちょうどあの黙々とした無心に身体を焦がしつづけている蛍の火にじつと見入っている時と同じ気持になり、・・・」
赤ちゃんの泣き声は、混じりけのない真剣なもので、お登勢はそれが好きだったと云うのです。
私は、何だか自分の至らなさの一点を鋭く突かれたような思いがしました。
子供の泣き声とはいったい何だろうか。今の自分はその声をどう受け止めているのだろうか。
子供が泣くのは当然なはずだ。自分の子どもだったらどう受け止めているだろうか。それにもまして自分も赤児だったではないか。そんな思いがかたく固まって神経質になっていた胸を溶かし始めました。
「赤児の声は鳥の声」と云った言い方も思い出しました。赤ちゃんの泣き声をうるさいなどと思うのは、鳥の声に文句を言っているのと同じです。自然世界の声なのです。それをうるさいなどと感じ原稿を書けないなどとは下等な人間だ。そんな思いがしてきました。
晴れた日曜日、お向かいの?姉妹?の散歩に出会いました。目礼してすれ違っただけですが、私はあの泣き声の子どもなのだと確信しました。確信すると同時に胸のつかえがはっきりと取れました。その日の夜からイヤホーンは使っていません。3歳の女の子がお風呂を嫌がって泣くのも分ってきました。その妹?が泣くのは、寝る前です。規則正しく泣いているのは健康な証拠です。聞いていて自分の頬がゆるむのがわかります。何だか嬉しくなるのです。
こんな話を家内にしたら、もう50年も前の恩師の話を持ち出した。
「近代文学館の館長だったO先生はきびしい先生だったけど、小学校のチャイムの音が好きで引っ越し先を決めたと云ってたわ、やさしい先生だったのよ」と。
O先生が苦手だった私はその話には乗らず、「江戸時代の長屋でうまい酒は、子供の泣き声を肴にするって云うよ。孟母三遷にも近いかな」などとわけのわからないウンチク話で逃げた。
壁一枚の庶民の生活。隣人同士なんでも見通しの生活が少し前までは当たり前だった。閉鎖的静けさを権利とするような時代が来ているのかもしれない。私もそれに流されているようです。
現代、寛容と云う言葉が忘れ去られているような気がします。
乳母車が電車に乗るのを迷惑がり、嫌な顔をするのは日本人だけです。中国でも、アメリカでも、フランスでも、この話題を持ち出したら一笑に付されました。ホームで秩序正しく整列し、扉が開くやいなや、席を奪い合い、老人が来ても、妊産婦が来ても、知らんふりでスマホに向かう。こんな光景は日本以外のどこにも見られない光景です。
秩序がやさしさを忘れさせたのです。
電車で隣り合わせになった赤ちゃんが私の顔を見ると急に泣き出しました。若いママが私にごめんなさいとしきりに謝ります。私は赤ちゃんの耳元にそっとささやきました。
「こんにちは!」
赤ちゃんはびっくりしたように一瞬泣き止み、ママは不審に私を見ました。
*
 学園では、6歳以下の子供のことを考える「おさなご発見U6ひろば」の多彩な催しが、11月22日・23日と行われます。
学園では、6歳以下の子供のことを考える「おさなご発見U6ひろば」の多彩な催しが、11月22日・23日と行われます。
最高学部もこれに積極的に参加します。榎田二三子先生の講演もあります。このポスターは学部生のボランティアです。
これから、子供たちと正面から向き合うことになる若者にとっても貴重な時間となるはずです。もちろん、孫にメロメロの私にとっても、隣の赤ちゃんの泣き声を聞く私にとっても大切な学びです。
2017年10月24日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)