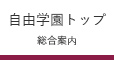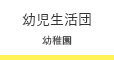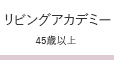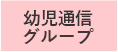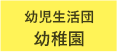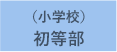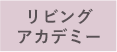『東京人』11月号の「特集 没後10年 井上ひさしの創造の世界」に一文を書いた。「江戸 ことば遊びやパロディ、戯作のエッセンスを見事に凝縮」と題したもの。
井上ひさしが亡くなったのは、2010年(平成22年」4月9日、2011年東日本大震災の1年前だ。私が、震災後の三陸を歩いたのは2012年の4月の初めだった。震災後の三陸を見ておきたいと思ったのだ。
浜辺に沿った宮古の櫛が崎は、かって古い遊郭跡の町並みを残していたが、跡形もなく消えていた。
ひょっこりひょうたん島のモデルとされている大槌町の蓬莱島は、霧のせいもあっただろうが、すぐ手前にあるはずの島がよく見えなかった。島の灯台も神社の鳥居も倒壊した・・・とその時海を見ていた漁師さんから話を聞いた。
島影を見ながら、井上ひさしのいくつかの作品を拾い上げ、記憶をたどったのを思い出す。
その後、蓬莱島の灯台は平成24年に再建され、島に生き残った・・、ちょっと大柄の弁財天も修復された。
早稲田大学演劇博物館の後藤隆基は、「3・11後、そして今、再び響きだす言葉」と題して、<没後の10年間に起きた、津波・原発事故・コロナ禍で「井上ひさしがいたら・・・」と無理を重々承知のうえで思ってしまうのだ。>と書き記している。
偉い?作家が亡くなると、メモリアルな年に追悼号が出る。その多くは感傷的な思い出話だったり、ファンの引き倒しであったりする。作者の実像をくもらせているような追悼特集もたまに見かけ、好きだった作家から離れてしまうこともあった。
『東京人』の今回の特集は、そんな通俗的追悼特集を越えているものだ。
井上ひさしの傍にあった人たちの味のあるエピソード披瀝に加えて、この10年間で失った言葉の意味をもう一度問いかけてくるような特集である。
野田秀樹と赤坂憲雄の対談「諧謔精神で貫いた、その批評のまなざし 東北そし て国家」の井上ひさしの文学へのこだわりにも新鮮な指摘を感じた。
て国家」の井上ひさしの文学へのこだわりにも新鮮な指摘を感じた。
井上ひさしの生原稿、創作メモも満載だ。少し丸まった驚くほど律儀なメモだ。活字では到底感じることの出来ない言葉の立ち上がりを感じることが出来るのも魅力だ。
私の書いたものにも少しふれる。
8月中旬から、手当たり次第に井上ひさしの作品を読み、DVD化されている戯曲はすべて見た。本棚4段が完全に井上ひさし関係の書籍で埋まった。
締め切り直前まで迷いに迷って筆が進まない。
自分がロック座でアルバイトをしていたことと井上ひさしのフランス座経験を重ねたり、何とか江戸時代をテーマとした作品と浅草物を結び付けようともがいたがうまくいかない。
浅草ドック座のストリッパーマリア(『珍訳聖書』)と唐来三和(「戯作者銘々伝」)の女房のお信を、結び付けてみたり、「江戸の夕立」と、東北を流浪した浄瑠璃語りの記録『筆満可勢』との関連をあぶりだしたいなどと考えたり、従来指摘されていない江戸物と井上ひさしのことを新たな言葉として書き継ぐのが我々残されたものの役割ではないかなどと思ったが、結局は徒労だった。
落ち着いたのは、井上ひさしが直木賞を取った『手鎖心中』論だ。
この作品を初めて読んだ昭和47年(1973)、私は大学院の学生兼高校の教員だった。仲間との読書会で、この作品を酷評した。
安っぽい江戸の青春ドラマだ。江戸の戯作に及びもつかない。人気作家に直木賞の勲章をぶら下げるだけだ、なんぞと啖呵を切ったのを覚えている。
今度、50年近くぶりでこの作品に向き合った。江戸の戯作と比べての違和感は相変わらずだったけれども、平賀源内という戯作の背骨を失い流行に身を寄せる以外に道のない若者の哀しみが胸にしみた。
キーワードは、江戸の反吐。井上ひさしの戯曲「小林一茶」、緞帳が下りる舞台、奥信濃に帰る一茶がつぶやく、「江戸は反吐」。それと『手鎖心中』の語り手十返舎一九が出会う、煙草を喫い続け煙で絵模様を描く太鼓持ち(煙花師)の反吐。屁で三味線を弾き、鳥の声を真似る放屁師の<業>を平賀源内の吐き散らした反吐だと云ったのは森島中良。
「反吐は故郷を捨て、江戸で名声を得ようとする戯作者のもの」「反吐は戯作者の地獄の坩堝」
そしてそれが江戸のエネルギーであり闇を見ることの意味だと書いたつもりだが・・・。
井上ひさしが亡くなったのは、ちょうど今の私の年75歳だ。今生きていれば85歳ということになる。
大学の対面授業も再開された。秋期の授業第一回は小沢昭一演じる、井上ひさし作「唐来三和」のDVDを見ることにした。「唐来三和」は吉原が舞台、その小沢昭一の解説・独演はまさに絶品。この公演が十九回も高校で演じられていることも今回の特集での矢野誠一の文章で知った。
2020年10月6日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)