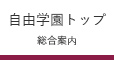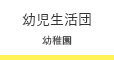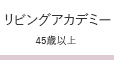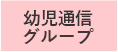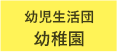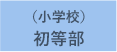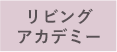天城山荘での女子部高等科2年生の修養会に参加した。
どんな話をしようか迷ったが、自由の意味をもう一度問うてみたいと思った。明治時代、自由と云う言葉が、一時流行語のように使われた時代があった。自由民権運動前後と云うべき時代だ。明治7年(1874)の民撰議院設立建白書の頃から始まって、明治23年(1890)の帝国憲法による総選挙頃までの時代である。
羽仁もと子が生まれたのは、明治6年(1873年)、上京したのが明治22年(1889)、明治女学校に入学したのは明治24年である。自由と云う言葉と共に羽仁もと子は育ったのである。羽仁もと子の青春時代、つまりこの修養会に参加している君たちと同じ頃に自由と云う言葉に大きな憧れを持っていたことはたしかなのである。
当時の自由と云う言葉の持つ意味をもっともよく象徴しているのは、自由と対の言葉で使われた、<自主>である。自立と同じ意味である。自主と自由は、ほとんど区別なく使われたのである。自主・自立なくして自由は成り立たないのである。自由民権運動が、藩閥政府の言いなりになる事からの解放を目指し、自分たちのことは自分たちで決めると云う強い意志に基づいていることを考えればよく理解出来るであろう。
今日、修養会に参加する前に、本当は詩人の石垣りんの生まれ故郷であり、資料館のある南伊豆市を訪ねようと思ったが、残念ながら資料館は工事中であった。伊豆で行うと云うことで、石垣りんの詩を紹介したい。りんの詩の中ではもっとも有名なものかもしれない。
表札
自分の住むところには
自分で表札を出すにかぎる。
自分の寝泊まりする場所に
他人がかけてくれる表札は
いつもろくなことはない。
病院へ入院したら
病室の名札には石垣りん様と
様がついた。
旅館に泊っても
部屋の外に名前は出ないが
やがて焼場の罐にはいると
とじた扉の上に
石垣りん殿と札が下がるだろう
そのとき私がこばめるか?
様も
殿も
付いてはいけない
自分の住む所には
自分の手で表札をかけるに限る。
精神の在り場所も
ハタから表札をかけられてはならない
石垣りん
それでよい。
私はこの詩ほど羽仁もと子にふさわしい詩はないのではないかと思う。おそらく羽仁もと子は、世間でよくあるように、羽仁吉一という表札の隣に、もと子と書かれることをこばんだであろう。また本人がその意志を強く持たなくても、彼女を継承した者たちは、つまりわれわれは、「羽仁もと子」それでいいと考えたのである。
ここで云う表札は、家の前にかける表札だけを意味しているのではない。自分の胸にしっかりとつける表札である。羽仁もと子は、書くと云う行為によって自立を求めた。書くと云う行為は、孤独であり、誰の助けも得ることのできないものである。多くの取材協力があったとしても、書く行為は絶対孤独である。そしてその絶対的孤独の行為の中で、多くの他者との結びつきたいと考えるのが書くと云う行為なのである。つまり、孤独が生んだ関係性とでも云い得るであろう。きりきりと追い求めるような孤独の中で、他者のことを考える。
羽仁もと子が、日本で始めてのジャーナリストとして喧伝されるのも、その後の生き方の中で、<自立>を求め、<自由>を勝ち取る教育を実践したからである。そしてもう一つ詩を紹介したい。八木重吉の詩である。
素朴な琴
この明るさのなかへ
ひとつの素朴な琴をおけば
秋の美くしさに耐えかねて
琴はしずかに鳴りいだすだろう
八木重吉の死後に刊行された『貧しき信徒』に所収のものだ。ここに思想も哲学も入る余地がない。そこが石垣りんの詩とは異なる処だ。「この」という一言で、秋の日の美しさがしみいるように私たちの胸を打つだけなのだ。その秋の中に置かれる琴は、高級なものではない、平安朝の物語に語り継がれたような伝説的な琴でもない。平凡な生き方の中で素朴に正しさを追い求める人の心のような琴なのだ。さびしいがゆえに優しくなれる深い自立と云ってもいい。それが、秋の美しさに呼応した時鳴りいだすのだ。秋の美しさは、心の奥にひそやかに、たしかに波打つ鼓動にささやきかける。一緒にと素朴な琴に・・。
素朴な琴が鳴りいだす。音楽のもつ飛翔は、境界を越える。孤独ははじめて共鳴の力を持つのだ。ひたむきな正直さは、「おけば」という仮定法を伴いながらも確信の如くに生まれていくのだ。
素朴な琴に重なるのは、方言丸出しの丸い顔の羽仁もと子だ。
2018年2月15日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)