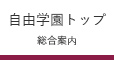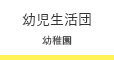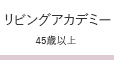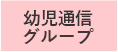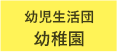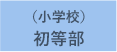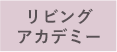少し長いのですが、話題になっている『君たちはどう生きるか』の感想を求められた月刊「よろず」5月号のインタビュー記事です。
◆身に染みたことなのか?
吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』をマンガ化した『漫画 君たちはどう生きるか』が人気のようです。私も読みました。
原作が出版されたのは約80年前の1937年、私が生まれる7年前でした。その頃は日本が本格的に戦争に突入していこうとする時期で、大正ロマンに象徴される自由主義的な空気が全体主義的なそれへと変わっていこうとする時代背景の中で出された「どう生きるか」というメッセージでした。
主人公のコペル君は、そうした時代の中で現実的な問題を敏感に感じ取っています。教養、差別、貧困、いじめ、勇気、といった現代にも通じるテーマについて論じ合いながら、この社会の中で自分はどのように生きていくのか、という命題に正面から向き合います。
学校教育の中で「どう生きるか」を考えていくのは「道徳教育」ですが、『君たちはどう生きるか』が出版された時代には「修身」と呼ばれていて、「親に孝行しなさい」「勤勉に励みなさい」といったことを教える重要な教科でした。
しかし、いくら学んでもいじめられたり、からかわれてつらい思いをするクラスメイトがいる。貧しい家の子はとことん貧しい。そんな現実にコペル君は直面し、悩みます。今だって同じです。いくら高学歴社会になっても、どんなに素晴らしい道徳テキストがあっても、立派な人間になるわけではない。そのこともこの本のメッセージの一つです。
文言として理解することと、実際に行動してそれが自分の身になっていくことが別の問題であることは、昨今のエリート官僚や政治家の言動からも明らかです。試験の問題文を読み解き、正しいほうに「○」を付け、難しい漢字が書ける、といった能力を持っていても、知識として得たことが自分の身に染みて捉えられていなければ、「隠ぺい」や「書き換え」もなくならないだろうと思います。コペル君に言わせれば、「アブラゲ」と呼ばれて嘲笑されているクラスメイトを助けることができるか、正義感を持っていじめっ子に立ち向かっていけるか、となるでしょう。
これを教師の側から捉えれば、点数的な評価には馴染まないこと、点数に置き換えてはならないこと、それこそが「どう生きるか」を考えていく道徳教育の根本的な価値であるということです。「修身」や「道徳」で何を教えるかということ以上に、どれほど自分の身で考えられているかということのほうが大きな課題なのです。給食費が払えない家庭の子どもの作文に潜んでいる心情や、うまく自分のことを表現できない子どもが書いた片言の文章も、立派な答案として手にして教師は読み取っていかなければならないのです。
ところが、文科省や教育委員会は、自分(国、省庁、学校、教師)が期待したことを言葉にできる者を評価する、という前提で教育を捉えています。幼稚園の子どもに立派な言葉を暗唱させて大人たちの前で声を揃えて言わせるのは、園長や大人の期待どおりに振る舞わせて「いい子」だと称しているにすぎません。子どもたちにしても、そんなこととは違うものさしで良い教師かどうかを見ているのです。帰宅途中についつい立ち飲み屋に心を奪われてしまう私には、「いい子になりなさい」などという言葉はかけられません。
財務省の決裁文書書き換え疑惑での関係者の発言も、型にはまった答弁に終始しています。でも、教育現場においても同じことが行われていないだろうか、と危惧します。校庭で遊んでいた子どもたちが校舎に入る前に一斉に手を洗い始める姿に違和感を覚えたと言う帰国子女がいました。手が汚れていれば自分の判断で洗うのが当たり前のことで、教師が無自覚に「いいことをやらせている」と満足してはいけないのです。
◆蛮勇ではなく曖昧さを
何でもできる子が「いい子」だとする教育的な価値観があるかぎり、いくら「主体性を育む」と言ったところで“型にはまった主体性”にしかなりません。それは明らかに矛盾しています。悩んでいる子、学業の継続が困難な子、家庭環境に問題を抱えた子などが発する切実なメッセージや鋭い感性を汲み取っていくのが教育であり、その対応次第で子どもたちに主体性が涵養されることを教師は心しておかなければなりません。
誤解を恐れずに言えば、型にはめるということが教育においては最もやってはいけないことです。私は受験に反対の立場でもありません。徹底的に勉強する時期は必要です。暗記すべきことは暗記したほうがいい。漢字も正確に覚えたほうがいい。だけど、それができなかったからといって、その子はダメな子ではないし、「正解」のないものにも点数を付けて評価をしようとすることには、私は反対です。
巷間に言われるほど日本は礼儀正しい国でしょうか? 電車の中でお年寄りや体の不自由な人に席を譲っているでしょうか? あるとき、同年代の日本人数名で中国の北京へシンポジウムに出かけました。地下鉄に乗る際、現地の人たちはドアが開くと一斉に飛び込みます。降りる人を待って乗るという秩序は見られませんでした。しかし、私たちが乗ると若者が席を譲ってくれました。本当に礼儀正しい国はどちらなのか。日本の道徳教育は本当に役立っているのか。私たちはどういう国を求めているのか。そんなことを感じました。そして、知識として道徳教育を行っているにすぎないから、列を並ぶこと、遅刻しないこと、ハンカチを忘れないこと、それだけに意味を置く社会になっているのではないかとも考えました。
規律を守ることのみが重視され、その価値観に基づいてあらゆることが白黒付けられていくと、一度失敗しただけの者に対して「一斉攻撃」を仕掛けることにためらいがなくなってしまいます。事実、今のメディアやSNSにその症状が表れています。言ってみれば、袋叩き状態を認める社会です。その行為は自分の主体的な行動などではなく、強権への無自覚な加担にすぎません。
前川前文部次官の中学校での講演について政治家から問われた文科省が、その内容や依頼の経緯を講演会の主催である名古屋市教育委員会に問い合わせたという報道がありました。ここで問題となるのは、「文科省の担当局が主体的に判断した」と言いながら、本当は誰かが政治的権威を傘に着て仕向けたことではないのか、という点です。文科省のための学校でもなく、政治家のための講演でもないのです。同様に、学校のために生徒に頑張らせるとか、国のために勉強させることはあってはなりません。国のため、学校のため、それらは言葉としては悪いものではないけれど、それが教育のすべてに当てはめられていくのは間違いです。でも、そういう傾向に社会全体が向かっているような気がしています。
これが極まると、独裁国家になります。融通の利かない、失敗に不寛容な、一つの正しさだけを価値とする、自分ファーストの社会です。現在、世界がその傾向にあればなおのこと、教育を型にはめることのないようにしなければならない。
では、野放図でいいのか? そんなこともありません。大事なことは「曖昧であること」です。それぞれの違いを認めるという教育の前提に立つならば、まさに曖昧さで対応していくしかないのです。
人間は迷います。白黒つけられなかったり、言うべきことを言えなかったり、迷うことが人間的特徴でもあるとするならば、曖昧さを打ち消そうとする権力や仕組みは、社会を非人間化しているようなものです。間違っても教育がその片棒を担ぐようなことになってはいけない。主体性を奪うのは、あらゆることを型にはめようとする圧力だったことを日本人は戦争中の経験から反省したはずです。
白黒つけられずに悩んでいる人、言えないことを抱えて苦しい立場に追い込まれている人、そういう人たちから自分に対して何が照射されてきているのかを受け取らなければいない。受け取るのは教師であり、学校であり、国です。
迷う。悩む。ためらう。心が痛む。どれも人間らしさの表れです。型どおりにはいかない人間だからこその心情です。でも、蛮勇などではなく曖昧さこそが「勇気」につながることなのです。迷いに迷い、その果てに出てきた言葉が人に勇気を与えることを私たちは知っています。むしろ、そのような言葉に励まされてきたのです。
◆痛みを共有する
ずいぶん前のことですが、一家で夜逃げせざるを得なくなって急に学校に来なくなった生徒が、こっそりと私に手紙を送ってきました。それに対して私は、手紙が来れば返事を出し続けようと決めました。30年前のその日以来、手紙のやり取りが続いています。
私の経験から言えば、退学せざるを得ない子に別の学校を探してあげるのも、授業料を払えなくて辞めていく子の進路相談に乗るのも、児童相談所に「どうか、後のことを頼みます」と頭を下げるのも、校長の役割だろうと思います。辞めていく子に対して自分からは縁を切らないでいようとする覚悟が校長や教師には必要です。そこが教育に携わる者に問われる「どう生きるか」なのだと思います。
コペル君もそうですが、取り返しのつかない後悔や失敗のときに、実は新しい経験が蓄積されていくのが人間です。後悔や失敗を意味のあるものにするためには謙虚に自分を顧みなければいけない。私自身、まだ若い定時制の教師だった頃に、遅刻してきた生徒に対して「後ろに立ってろ!」と言い放ったことがありました。生徒は、そのまま教室を出ていき、二度と学校に来ることはありませんでした。これが私にとっては「教師として、どうあるべきか」を自問する原点になっています。事あるごとに思い出す出来事です。
教室や職場でいじめられたり不条理な仕打ちを受けている人がいたとして、いじめっ子や上司に「そんなことは、やめろ!」「それはパワハラではないですか?」と勇気を持って言うのは簡単ではありません。誰だってそうだろうと思います。しかし、言えないということの痛みを感じ合うことはできます。いじめられている子がいたとして、それをクラスメイトは教師に報告できずに苦しんでいるかもしれない。「その気持ちは、先生にもよく分かるんだ。かつてこういうことがあってね……」と、痛みの共有をすることは大人と子どもの間でも可能です。「いじめを見たら先生に伝えること」という行動が正しいことは頭では分かっているけれど、それができない。そういう子を「ダメな子」と判断するだけで生徒の痛みを感じなくなったら、教師は終わりです。
人は、正しいことを共有していれば安心できるわけではないのかもしれません。規則通りの行動ができないことの痛みや悲しみこそ共有意識として必要であるように思います。それがお互いに感じられたとき、自(おの)ずから一歩を踏み出すことができていく。7年前の震災のときに私たちが経験したことも、それだったのではないでしょうか。
◆つらさを持って神の前へ
小学生やもっと年齢の低い子どもたちに「光の子らしく歩め」というニュアンスの言い方をします。でもその言葉のまま大人にはなれません。必ず「闇」というものを意識し始めます。むしろ、「闇」が共有されて「共に」というあたたかい場が生まれることがあります。「闇」とは、迷い、痛み、悲しみ、のことです。
「光」は「光」として単独で存在しているわけではありません。「闇」があってこその「光」なのです。「闇」があるから「光」が意味を持つのです。
梅原猛の著書『法然 十五歳の闇』を読むと、法然が「闇」を見たことで専修念仏の浄土宗を広める人になっていったことが分かりますし、他の開祖たちも同様です。仏教者だけではありません。アウグスチヌスのようなキリスト者も非常につらい個人的体験によって「闇」を見た。そのことが後々、キリスト教思想に厚みを与え西洋思想史における重要な役割を果たしました。
だから子どもたちに言いたいのです。つらい経験がなければそれに越したことはないけれど、もしそんな状況になっても、嘆き悲しむことで終わらせずに、そこから出発し直した人たちがたくさんいることを覚えておいてほしい、と。
原発事故で避難を強いられた子どもたちが、避難先でいじめられるようなことが起こる。そういうときにこそ教師を含めて地域の人も一緒に、子どもたちと手をつなごうとする意識が生まれてほしいのです。「光」の部分にではなく、生きることのつらさという「闇」の部分に生まれる共有意識が、社会には必要なんです。それは、原発に賛成か反対かという是非論を超えた人間的な態度です。
私たちは、日常の中でそうした瞬間に度々遭遇します。患者さんが骨折して「痛いよー!」と訴えながら病院へやってきた。そのとき、「痛いですね、痛いですね」と近寄っていく看護師さんがいる一方で、「待ってください、ドクターを呼びますから」とそっけない応対をする看護師さんもいる。私たちに問われているのは、「痛いよー!」に対して「痛いね」の寄り添い方ができるかどうかです。これも「どう生きるか」の一場面です。
教師が二者択一を生徒に迫ります。「進学するのか? 就職するのか?」「学校をやめるのか? どうするんだ?」という言い方はよく聞かれます。私自身もそうでした。でも、生徒は悩んでいたんです。自分の気持ちを言えない状況を抱えていたんです。それが生徒との共有の瞬間であったのだということを歳を重ねるにつれて気づかされてきます。そんな後悔の告白しか語れることはないけれど、教師として後に続く人たちには聴き取っておいてほしいと願う気持ちがあります。
私は真面目なクリスチャンではないけれど、自分が死ぬときに何を持って神様の前に行くのだろうか、と自問してきました。「こんな幸せを与えてくれて、ありがとう」と言おうと、ずっと考えていました。ところが、だんだん変わってきました。「この世には、こんなにつらいことがありますよ。子どもたちは、いじめで苦しんでいますよ。水俣病の問題だって、まだ終わっていないんですよ」という思い出を持っていこうと思うようになりました。もしかしたら、そう考えながら今を生きるほうが他者への謙虚さを失わなくて済むのではないか、という気がしています。幸せを持っていったところで、それは自分が良かっただけの話にすぎないのですから。
定時制高校、進学校、女子大、大学など50年近くを一介の教師として生きてきて、やっぱり思い出すのは、途中で学校を辞めていった子どもたちのことです。クラス会に呼ばれても、そこに出席していない教え子たちのほうが気になります。そして思うのは、そういうことを気にかけている、それが教師の役割なのではないかということです。
高校野球では、甲子園大会で最後まで勝ち残るのは1校で、それ以外の約4,000校は必ず敗者を経験します。勝者に光を当てるだけでいいのだろうか? 勝者の言葉が他の敗者たちに響くだろうか? 敗者がやっとのことで言葉にしたその表現の中に、彼らの素晴らしさを見い出そうとしているだろうか? 大好きな高校野球を見ながら、そこに自分を重ね合わせています。
2018年4月30日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)