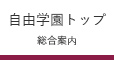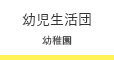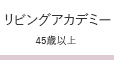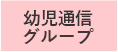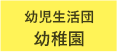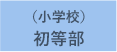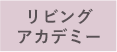注記:( )内は原典振り仮名。
羽仁もと子にとって故郷八戸とは、いかなる意味を持っていたのか。そんなことを考え出したのは、自分が故郷函館のことを、この頃しきりに思うようになったからだ。
17歳の時に父を亡くし高校の卒業式にも出席できずに函館を離れた私にとって、故郷は痛恨の思いの積もった場所であった。その故であろう。私の故郷への感情は複雑だ。
今年3月の始めに佐藤泰志の墓詣でをした。佐藤泰志は、5たび芥川賞候補になりながら、受賞かなわず41歳で自殺した函館出身の小説家だ。一時期は、村上春樹・中上健次と並び評されたが不遇であった。最近は「きみの鳥はうたえる」など函館をロケ地とした映画も公開されている。
薄っぺらなトタン屋根が続く泰志の生まれた家近く、海風を受けながら、大森浜で石川啄木の像を見た。啄木の哀歌と泰志の痛恨が重なる。そして故郷とは何かを問い詰められているような気がした。
そんな時に羽仁もと子の故郷への思いを寄せる一文に出会った。
羽仁もと子著作集第20巻の序にかえての一文「ふるさと、又ふるさと」だ。
この文章はいささか不思議な文章である。題名は「ふるさと」と仮名表記であるが、文章中は漢字で書かれ、そのフリガナが「こきょう」と「ふるさと」に分けて書かれている。長い文章であるならば、統一が出来なかったのであろう、筆のおもむくままであろうと解釈も出来ようが、500字ほどの文章で、これはやや不自然ではないか。羽仁もと子の故郷に寄せる思いを考える手掛かりにもなるのではないかと思われてきたのだ。その文章の全文を引いておく。
「ふるさと、又ふるさと」 ー序にかえてー
故郷(こきょう)と聞けば第一に思い出すのは、その寒む寒むとした暗さの中で、春を待っていたあの心持である。私は年中明るい暖い天地を恋い慕っていたのである。
なつかしい私の故郷(こきょう)は、また私にその東北語を、固く固く教え込んでしまった。要領のよいことは決して出来ないと、知らない間にそう私を強く支配しているのも故郷(ふるさと)であった。
鈍(にぶ)い言葉で要領の悪いことをいい、鈍い身体で要領の悪い動き方をし通している、そうしてそれは私の故郷(こきょう)からの嗣業(ゆずり)である。私は長いこと唯そう思っていた。私は故郷(こきょう)を憫れむことが出来ても、真実(ほんとう)に愛することが出来なかったようである。
その重苦しい殻の中で、私は知らずに考えさせられてしまった。要領よくするために考えたのではなく、唯何が本当かを考えさせられて来た。それも知らずにそうした方面に向けられていたのである。この頃私はそのことを、みどりごの心と呼びたくなった。そうしてそれもまた私の故郷(こきょう)の嗣業(ゆずり)であった。故郷(ふるさと)はなつかしい。故郷(ふるさと)はありがたい。
しかも私の今故郷(ふるさと)といっているのは、あの東北の海岸ではなくて、たましいの故郷(ふるさと)、天の故郷(こきょう)のことである。
宿命を苦しみ、光を慕って、遂に真の故郷(ふるさと)を望み得るために、寒く貧しい地上の故郷(こきょう)が必要なのであった。永遠になつかしい東北の山河よ。一時(じ)も早く汝自ら、そのわびしい宿命の中から救われてくれ。」
(昭10.7)羽仁もと子著作集第20巻『自由・協力・愛』序文。
私の故郷函館と同じように、八戸も又春の訪れを切望する町である。もと子は、冬の暗さ寒さが、故郷を思う時にまず思い出すことだと云う。そして訛りの強い東北弁が、重苦しく武骨に自分を支配し、知らない間に自分を固定的な殻に閉じ込めたと云う。もと子が、晩年に至っても、東北弁が抜けなったことはよく知られている。直接もと子の教えを受けた人は、語り口の訛りが強くて聞き取れなかったと冗談交じりで話す。年老いてももと子は、故郷の手形のように東北弁を脱することが出来なかった。
否、自分の意志で(多くの人はお国言葉と標準語を使い分けることが出来るのだ。)彼女は自分の言葉を、<嗣業>として身にまとっていたのである。
嗣業、この言葉は、『日本国語大辞典』・『広辞苑』にも掲載がない。少なくとも一般的用法ではないが、『旧約聖書』にはしばしば使われ、もと子もよく使っている。『教育三十年』「年のはじめの子供と語る」の「われわれの領分」でも、『旧約聖書』を引用して使っている。難解な言葉であるが、『旧約聖書』では、神からいただいた土地を所有することを意味し、ユダヤ人の「嗣業の土地」思想は極めて強固なものである。
嗣業という表現は私の中で硬骨なものだ。耳慣れているのは、嗣続という表現で、それに近いように思えてならない。
『正法眼蔵』に、「仏祖の祖風を嗣続するより、摂心無寝・・」とか、「苦学怠らざれ、仏祖の命脈まさに嗣続すべし」などとある。「業」も強い表現だ。「やるべきこと、暮らしていくための仕事、職業、事業」などと使うが、これも『正法眼蔵随聞記』に「しばらく存命の間、業を修め学を好まん」などとある。私はこの語が禅語の影響を受けたものであろうかとはじめ思った。
もと子が故郷八戸でもっとも影響を受けた人物は、後に総持寺貫主をつとめた曹洞宗の僧侶、西有穆山(にしありぼくざん)である。穆山は、もと子と同郷の八戸出身である。『半生を語る』でも、多くのページを割いて彼女は穆山について記している。その穆山の記したものに、『正法眼蔵啓迪』がある、明治の時代の刊行だが、これはその時代の多くの若者が善にひかれる時に読んだ必読の書である。
もと子は、最初の結婚が破綻し、羽仁吉一と新たな生活を営むまでの間、生涯でももっとも苦しい時を経験している。この時期ついて、もと子は、次のように語っている。
「私は西有穆山師のことを思い出した。禅門の高僧穆山さんは、私の国の貧しい豆腐屋の子供で、徳行と逸事に富んだ方であった。私は西有さんのおいでになる所を知りたいと思った。」(「半生を語る」)と記し、彼女は方々を探し回り、退隠し静岡県の島田にいた西有師を訪ね、三日三晩老師の慰めの言葉を聞いている。
「穆山老師にお目にかかった時、そうしてそれが見れば見るほど尊敬すべき人であった時、その方が手紙を見て待っていたといって、ただのおじいさんのように打ち解けて、本当に行き届いた親切をもって話したり尋ねたりして下さった時、どんなにうれしかったか。」(同上)とその出会いに感謝し、「私は近い過去において、結婚に敗れた敗残者の身の上である。」(同上)と述べている。敗残者などと云った言い方の中には離婚が深い傷であったことが想像されよう。故郷に離婚したこともまだ告げられないでいると云う状況からも彼女の心理を推し量ることが出来る。離婚は故郷への裏切り、背信のように思えたのかもしれない。実家への後ろめたさは、おそらく当時の離婚経験者における共通のものであろう。まして自分は両親の離婚を経験しているのである。「敗残者」と記すその思いは如何ばかりであったであろう。
そして老師は、彼女の両親のこと語る。「老師の話して下さった、そのありのままな生い立ちの記憶には、人のよい夫を助けて、大勢の子供を育ててくれた、きかぬ気の母に対する、思慕と同情があふれていた。女は大切なものだと何度も言われた。」
そんな老師の話をきっかけにしたのであろうか、「私は私の家にも離婚のこともそれ以来のことも知らせてやって」、弟と落ち着いた生活を始めたのである。もと子は家を出た父については多くを語っている。だが、若かった頃の母についての記述はあまり多くはないようだ。だが、ここに記載されている「女は大切なものだと何度も言われた。」という老師の話は彼女の人生の転機を考えるとき重要な一文である。
又、「老師のおいでになるお寺は、そのころの私の心のホームであった。」と記す。尼になることを希望し、それを祖父が「あの子の望みはこれまですべて妨げずに来ましたけれど、それだけは考えなおすように。」といったと云う話で成就しなかったことをのせている。彼女の心の痛手を救済する尼となる行動は、実現しなかった。しかし、老師の慰めの中で彼女は故郷への思いの転生を遂げたのである。
それは、「宿命を苦しみ、光を慕って、遂に真の故郷(ふるさと)を望み得るために、寒く貧しい地上の故郷(こきょう)が必要なのであった。」という一文によく表れている。<ふるさと>と<こきょう>は、対峙しているのだ。「宿命を苦しみ、光を慕って」とは、自分の人生に訪れた不幸を宿命とし、西有穆山をはじめとする多くの人との出会いのことである。(もちろん特筆すべきは愛する吉一との出会いであろう。)それを光として慕うことによって得られたのが<ふるさと>だ。その<ふるさと>を自分のものとするために、つらい風土である嗣業の<こきょう>があったのだ。
たましいが有しているのは<ふるさと>であり、天にあるのは<こきょう>であるという。誤解を恐れずに云えば、それはあたかも、旧約聖書の世界が<こきょう>であり、新約聖書の世界が<ふるさと>であると感じるのと似ている。
翻って私自身のことを思う。私にとって<ふるさと>と呼べるのは、父母と重なりなつかしさに満ちた函館である。それは、また同時に<こきょう>と呼ぶ彼の地の暗く冷たい風だ、野卑な漁師言葉の匂いだ。こきょうと呼ぶその地を羽仁もと子と同様に「真実に」愛することは出来なかった。しかし、<こきょう>への悔恨がなければ、今甘美に流れる<ふるさと>への思いもないのだ。魂の生まれ出る地が「ふるさと」である。そして今もとめ行かんとしているのは天と呼ぶ場所の「こきょう」である。
我々学園の創始者である羽仁もと子の魅力は、一筋縄ではつかみきれないところだ。私には、彼女の云う「天」が人生の帰結を指しているとしても、それが一つの宗教に縛られない禅をも含む大きな寛容の世界であるような気がしてならない。
【付記】
以上は6月8日に行われた読書会で御話したことの一部です。保護者会便りにも転載せてもらいましたが内容はかなり異なっています。羽仁もと子先生と記すべきところですが、歴史的記述を旨として敬称を略させてもらいました。
2019年6月20日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)