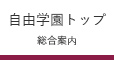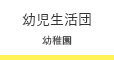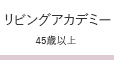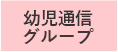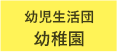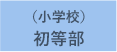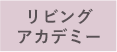今年の4月に明治座で公演された「二人のお国」の劇場用パンフレットに以下のような一文を書きました。「ヒトムレサワグ京の町1603年歌舞伎誕生」と題したものです。
*
「ナクヨうぐいす平安京794年」「イイクニ作る鎌倉幕府1192年」などと覚えた中で、「ヒトムレサワグ江戸幕府1603年」などと覚えた方も多いのではないでしょうか。
1603年(慶長8年)、この年の2月に徳川家康は征夷大将軍となりました。そして、4月4日から3日間、家康は二条城に全国の諸大名や有力公家衆を集め能楽を挙行し、饗宴をくり広げ、「天下一」の覇者であることを誇示しました。
しかし、同じ年頃、京都の町でもっとも話題に上ったのは、家康の天下宣言ではありません。同じ京都の町で話題になったのは、後に<かぶきおどり>と称される、<ややこおどり>でした。「ややこ」はおさなご、少女の意味です。
1500年ころから伝えられる「ややこおどり」から1600年ころへの「かぶきおどり」への移行を、服部幸雄氏は、『歌舞伎成立の研究』(風間書院)で、「この慶長8年ごろを境として、名称の交替が行われたのである。」と述べ、その理由を、京におけるかぶき思想・風俗の流行のあること、また多くの芸能者が「歌舞伎踊り」の名称を用い始めたことをあげています。
慶長8年5月6日に記録された公家の日記(『時慶卿記』)では、女院の御所で宴が行われ<ややこおどり>と呼ばれた、それが雲州、出雲の「女楽」であったと述べています。又やや時代が下った時期に編纂された『慶長日件録』では、「かぶきおとり有之出雲国人」と記されています。編年体の江戸初期記録『当代記』では、4月のこととして「カブキ躍り」の記事があります。
「かぶき」は、「傾く」です。正当なものへの異端的意識の表れです。時代への反発と云ってもいいでしょう。時代の流れに従順なかわいらしい少女が、一皮も二皮もむけて、時代の空気をたっぷり吸い、時に放埓に時に時代に抗い、自律的に大人の女に変身していった姿と云ってもいいでしょう。
少女、<ややこ>はファションの先端を走り、サブカルチャーを形作っていくのです。それは現代においても変わらない文化変貌です。
徳川の政権が、これから250年以上も続くとは、京の大衆の誰もが思っていなかったでしょう。京の人びとは、長く続いた戦乱で権力がいかにもろくはかないものであるかを知っていました。つい先ごろには、豊臣秀吉の権勢が京の町を凌駕し町の人々の心も捉えていたのです。それもつかの間、3年前の関が原の戦いは権力構造を豊臣から徳川へと大きく変えていったのです。
京の大衆は、生々流転する世の中に不安を感じながら一時の快楽を求めていたのです。
人はそれを浮世の到来と呼びました。当代、人々に知れ渡った歌の歌詞にも、
「いなものじゃ、不思議なものじゃ、心はわが物、自分の心のはずが、自分の思うままにならないものだ、」と歌っているじゃないか。この世の中思うことがかなわないから、浮世なのだ。刹那刹那に軽く世を渡り、貧乏なんか気にせず、楽しくいこうじゃないかと述べています。(「浮世物語」)
その浮世の頂点にあったのが、出雲阿国と云う偶像です。彼女について多くの不確かな部分があります。阿国が一人であるか、当時の芸能集団の総称であるかは、明確に結論を出すことは出来ません。当時も今も、伝説の女は、当時の芸能集合体の象徴として伝承の中で記憶に刻まれてきたのです。
浮世の春を謳歌する庶民、大衆は、サブカルチャーの旗手として「かぶく」女を<天下一>にのし上げたのです。
彼女は、出雲の巫女と称し、神の使いの如く祝言の放浪芸を振りまき、ある時は男装し、茶屋通いに踊りと歌を交え男(実は女が)と戯れ、観客をエロティシズムに酔わせました。扮装は、怨霊のメッカ北野天神と競い合うかのような紅梅の肌着、舶来仕立ての唐織の小袖に、燃える赤地金襴、萌黄の羽織。それは、今までの観客たちの見てきた「能」仮面劇とも異なり、目を奪う華麗さを現出させたのでした。ときめく演者の<性>の躍動がやってきたのです。
またある時は、黄金つくりの鍔に白鮫鞘の太刀を帯び、黄金の鞘に赤い大脇差を引っ提げていたのです。首に念仏講でまさぐった大数珠をかけた者もあれば、南蛮更紗の袖なしの胴着を小袖に重ね、水晶のロザリオと十字架を胸にかけている姿もあったのです。
京都の教会がキリスト教禁教令で破壊されるのが、慶長17年4月です。その10年程前の日々です。1600年を境に約1万人の洗礼者が出たと云う時代です。キリシタン風俗は夢の輝きを持っていたのです。
絢爛なる異相「カブキ者」の狂乱が続いたのです。その上に、南国の風に乗ってやってきた甘美な三味線の流行が、淫歌に火をつけたことも言い添えておきましょう。
そしてこのカブキ風俗が席捲したのは、大衆のみではありません。武士たちも、皇太后つまり天皇の母や上層の公家たちも、階級も、男も女も越境したのです。
「女かと見れば男、男かと思えば女」、「仏者と見ればキリシタン」、「祝祭かと見れば怨霊」「つらい憂き世かと思えば浮き世」
境界を越えたトランスジェンダーのスト-リーは、<お国>の名を借りて憑依し、大衆を虜にしたのです。それは今も続く「歌舞伎」の始原です。
「ヒトムレサワグ京の町 歌舞伎誕生1603年」などと記憶したいものです。
*
以上がパンフレットに書いた全文ですが、少し書き足しておきたいと思います。
お国の倒錯劇<境界を越えたトランスジェンダースト-リー>は、中世の五山文学に見られるような男色文化の継続に発火点を与えました。異端とも取れる<かぶき>文化は、大衆の中に違和感なく溶け込んでいきます。白昼堂々と貴賎を問わず多くの人々が熱中した倒錯劇文化は、世界史的にみても古代ギリシャと日本の17世紀前半以外にはないのではないかと思われます。
その公然たる盛況ぶりの理由は、宗教的抑圧の希薄さや性への偏見が権力構造と結びつかなかったことによるものでしょう。男性と女性の性の異なりを明確化させて、偏見と差別を助長するような国家体制が、江戸時代初期においては希薄だったとも云えるのではないかと思います。
倒錯劇の流れは、やがて若衆歌舞伎の盛況につながって生きます。若衆好きの三代将軍家光の死んだ慶安4年(1651年)の翌年の承応元年(1652)に「若衆歌舞伎」が禁止されていますが、17世紀前半の時代は、若衆の時代とも云うべき男色文化が盛況の時を迎えます。
「若衆の時代」です。
寛永年間に刊行された『催(さい)情記(せいき)』は、若衆のさまざまな心がけを説き、衣装・化粧・持物・食事、さらに入浴・房事の秘技にまで細かに書き記している。若衆が念者(兄分)にいかに心を配りその気を引くべきかが述べられています。
『心友記』(寛永20年刊行、改題本寛文元年刊行『衆道物語』)では、その対象とする「少人」(少年)を12歳から20歳までの9年間と定め、それを三分し15歳からの3年間をもっとも美しい時期だとし、「此間は情の理非を深くつつしみ、道をすこしもたがはざるやうにして、たしなみもきよく、万事を世の常にして、心にもことばにも及ばれず盛んなる間也」と記している。情愛と分別心がこの時期に成熟し、少年らしい柔軟さをとどめているというのです。
又、寛永14年以後の作と云われている『田夫(でんぷ)物語』は、男色と女色の優劣論争を記したものです。
「それならば女道(にょどう)が卑しくて若道(じゃくどう)が華奢(きゃしゃ)であるという道理を問答し、どちらでも理の深いほうに従い、理の浅いほうが堪忍したらどうだ」ということで、論争が始まり、互いに女色・男色のよさを主張しあい、最後に女色側は、「若衆が世を保ち国を受け継いだという例もない。またそうあるべき道理もない。子孫が跡を継いだからこそ、国をも家をも保てたのである。その他空を飛ぶ鳥、地を走る獣、これらはすべて夫婦の語らいをしている。その方も日本が神国であるのに従い、神がはじめられた道を守れば、どんなにか恵みも深いことであろう。その方の非道をはやくやめるがよい」と、家族論・国家論さらに日本の神国論を展開して、男色側を屈服させ終わりになります。
最終的には、女色愛好側が常識論と権威を振りかざして終わるのですが、注目すべきは、女色支持者を「田夫者」(いなか者)、男色愛好家を「華奢者」(風流な伊達者)と作者がみなしている点です。ここに作者の羨望を読み取るべきでしょう。結論は作者がこの論争で意図したものではありません。この時代の作品は、いかなる悲劇であっても最後は祝言で終わると云う型を持っています。結論はいつも常識的なものなのです。作者はきっと当時盛んな若衆歌舞伎に関心を寄せ、若道・衆道の流行に心を躍らせていたに違いありません。それらを異風なるがゆえに新奇なものとして眺めていたのでしょう。多くの人の深層心理を代弁する作者の気持ちが、書名を「華奢物語」ではなく「田夫物語」としたのです。美意識を論じてきた物語りに、国家維持論を持ち出すなど全くナンセンスな言動であることを作者は十分知っていたのです。
田夫は「野暮」、つまり野暮らしです。田舎者を貶め、洗練された都会的美意識として「華奢」を持ち上げたのです。「華奢」の美意識が江戸時代の「粋」の美意識につながっていることもここでは記しておかねばならないでしょう。
『日本思想大系60近世色道論』の月報で評論家の中村真一郎は、「男色と女色がいずれがすぐれているかを論ずるのは、丁度、平安朝で春と秋がいずれが趣が深いかを論ずるのと同じような、もっとも流行したサロンの話題であり、そのためのパンフレットも幾種類も出ている。」と述べ、「「男色と女色とがいずれがすぐれているか」というこの設問がでてくるのは、男色と女色とがまず当時の性意識のなかで平等であった、ということが前提にあり、男性は男をも、女をも、自由に恋することができ、欲情の対象とすることができる、という観念を基礎に持っている。」「この設問が成立した以上、男性が男性に対して恋情なり性欲なりを抱くことが、稀におこる例外であったり、また起ったとしても恥じて秘めなければならないというのではなかった。男性の愛欲というものは、時に応じて男性にも女性にも向って発動するものであり、あるいは女性を相手にするより男性を相手にする方が、より高級であり、清潔であり、精神的要素が多いのかも知れなかった。男色女色優劣論での男色側の支持者は現に、そう主張しているのである。そこには女性蔑視の観念さえ横たわっている。」と記しています。
江戸時代初期、性は白日の下に開放性を有しながら、「性」のトランス、<交通>をうながし、日本のきわめて特徴的な芸能の母体となったのです。冒頭に掲げた明治座のパンフレットは宝塚のスターを主役に置いたものです。宝塚歌劇そしてもちろん伝統劇「歌舞伎」も、男装・女装が織りなしたこの時代の文化の継承であることは間違いありません。
そして、この時代の男色愛好の傾斜が、衆道の唯美主義的世界を浮き出させ、権力への批判的性格を内包して、井原西鶴という天才の手になる『男色大鑑』を生み出したのです。昨今、社会的問題への視座として「トランスジェンダー」が取り上げられています。
性的差別意識の強いキリスト教文化から距離を置いた鎖国状況の中で、日本が、いかに伝統的文化を育んで行ったかを、今こそ現代社会が直面する性の開放性とともに再考しなければならないようです。
2019年4月17日 渡辺憲司(自由学園最高学部長)